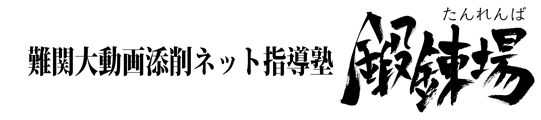2024年慶應義塾大学文学部小論文について
慶應義塾大学の小論文対策、しっかり考えていらっしゃいますか?
その対策としては「過去問研究」が最重要です。
今回、2024年慶應文学部小論文問題の解説を行います。
鍛錬場では、オンライン指導を通じてサポートいたします。
是非とも下記をクリックして、お問い合わせ下さいませ。
鍛錬場の紹介ページはこちらから

目次
2024年慶應義塾大学文学部小論文問題

まず、実際の問題を見てみましょう。
課題文
次の文章を読み、設問に答えなさい。
「競争」が自然選択を通じて成長や革新につながると考えられるようになったのは、十九世紀に入って産業社会が登場し、市場経済が資源配分メカニズムの中核的な役割を担うようになって以降である。
では競争の対象とは何であろうか。それは稀少な財・サービスと機会である。有名アーティストの公演チケットであれ、職場の管理職ポストであれ、限定品のブランドバッグであれ、それらは稀少と見なされるからこそ争いの対象になる。
そもそも稀少性とは、誰によって、どのように定義されるのか。私たちに馴染みがあるのは消費者の決める稀少性である。多くの消費者が求めるポケモンカードは、高値がついて稀少化する。カード制作会社が生産量を絞ることで、稀少性を操作できないわけではない。だが稀少であることそれ自体が広く認知されなくてはならないので、究極的には消費者の需要がカードの稀少性を左右する。
ここで注意を要するのは、市場でやりとりされる商品の枠からはみ出るような「資源」の稀少性が、政策的につくり出される場合である。たとえば私がかつて長期のフィールドワークを実施したタイ中西部の奥地で生活する人々にとって、森林の樹や草は自然に生い茂っているもので、そこから得られる諸資源は稀少であるとは認識されていなかった。しかし、その森林は国家から見ると、稀少な動植物を含む生物多様性の宝庫であり、重要な観光収入の源でもある。政府にとっては、森林は地域の人々の生活を制限してでも保護すべき稀少資源なのである。
他方で現場に目を移すと、地域の人々は森林局の役人の目から隠れるように森に入っては、生活に必要な物資を取り出していた。重要なのは、現場に暮らしているわけではない外部の有力者が稀少性の判定において大きな影響力をもつという点である。これまでは村人同士で調整すればよかった土地と森林に関する暗黙のルールは、国の政策や法律に置き換えられたとたんに機能しなくなり、人々の生活資源はローカルな管理者を失って争いの対象と化してしまった。
こう考えると、産業革命以降、稀少化する財や資源から排除されていく貧困層の存在が最初に社会問題化したのがアジアやアフリカの国々ではなく、欧米諸国であった理由が納得できる。放牧地の稀少化に伴って中世の末期から近代にかけての英国で二度ほど大規模に実施された共有地の囲い込み(エンクロージャー)は、共有地から締め出されて土地を失った人を貧困に陥れた。このときの「貧しさ」は、そこにある資源の総量とは全く別の論理によって生み出されたのである。貧困が単純に財や資源の総量の問題であれば、まずは物質的に貧しい地域でこれらの概念が広がるはずである。実際には、そうではなく欧米諸国で貧困が社会問題化したということは、「貧しさ」が相対的に決まるものであることを示している。
何が「まっとうな生活」であるかは、経済発展の程度によって変わるので、それに合わせて何が稀少であるかも変わってくる。稀少性の知覚はタイの事例のように、かつては誰でも使えていた資源を競争の対象に変えるだけでなく、以前の贅沢品を新たな必需品に変えてしまう。稀少な贅沢品の獲得の本質的な目的がモノそのものではなく、他人との差異を生み出すことであれば終わりがないのは当然である。
「パン」をめぐる争いは、お腹が一杯になったところで終了しない。人はすぐに他人よりも多く、おいしいパンを追い求めるよう駆り立てられる。「稀少性の拡大」が意味したのは、「稀少」の判定基準が一元化し、序列が明確化することであった。序列の明確化は競争の激化をあおり、競争は争いへと転化していく。
稀少な財・サービスをめぐる競争は、「発展の遠心力」となって末端の人々を生産に参加させ、財・サービスの総量を増やすという点で人類を豊かにした。しかし、そのプロセスに巻き込まれる一人ひとりの人間の視点からすれば、あらゆるものが稀少化して競争から逃れられなくなるのは苦しい。競争のよい面を維持しながら、その歪みを少しでも抑え込むにはどうすればよいのか。その答えは、競争と無競争の間に横たわっていそうである。まずは競争原理の限界を整理しておこう。
競争を通じて社会をよくするという考え方には三つの限界がある。第一に、ニーズや生きがいといった無形の価値を財やサービスといった利得に置き換えてしまうということである。大型のコーヒー・チェーン店が各地に広がる反面、その地域にしかなかった個性的な喫茶店がなくなっていくという多様性の消失も、競争の歪みの一つである。ガルブレイスが名著『ゆたかな社会』の中で論じたように、財・サービスの需要そのものは人間本来の選好というよりは、巧みな広告などの人為的な操作であおられている側面が強い。
第二に、価格競争の激化によって、モノの値段の背景にある人間の依存関係が見えなくなることである。価格を介して相手を打ち負かすという市場経済に特有の原理は、競争を下支えしている協力のすそ野(ここには、様々な無償労働を含む)に対する視野を狭めて、相互依存に基づく協力の価値を見えにくくする。その結果、報酬、インセンティブ、罰則といった「自己利益を追求する個人」の動機に働きかける、見えやすい制度づくりに人々の関心が偏ってしまう。格差と不平等がテロや地球環境問題の元凶であることは広く認められつつあるが、もし競争が格差の根源にあるとすれば、競争のあり方に手をつけることなく格差を根絶できようはずがない。
第三の限界は、競争が原料の確保とその利用手段の取り合いに焦点を置くために、経済活動そのものが究極的に依存している自然の存在を忘れさせることである。「肉や野菜はスーパーにあるもの」というイメージは、消費者の意識を自然そのものから切り離し、自然の存在を忘れさせる。生鮮食料品の値段が上がることに敏感ではあっても、食料品の生産そのものが化学肥料の投入などを伴って自然環境を劣化させている可能性は想像しにくいのである。こうして、人間同士の競争は自然の支配へと拡張し、間と自然の関係を取り持っていた各種の秩序を崩壊させるに至った。多くの伝統社会がもっていた、森林や放牧地などの共有資源を維持するための秩序が、貨幣経済と国家経済に編入される過程で失われたのはタイの森林の例で見た通りである。競争至上主義に立てば、より効率的な社会運営のために伝統的な共有の制度が葬り去られることは当然である。市場経済の世界が生み出した競争は、いつの間にか環境や生活に直結する実体経済を侵すようになってしまった。
ならば、私たちは「無競争」を奨励すべきなのだろうか。結論を急ぐ前に、無競争の問題点も自覚しておく必要があるだろう。たとえば、日本の一部の小学校では「順位をつけない徒競走」が行われていて、その是非が話題になることがある。負けた子供に劣等感を植え付けることになるというのが順位をつけない主な理由だそうだ。徒競走だけではない。学校の成績においても優劣の序列につながる相対評価ではなく絶対評価の重要性が主張されることがある。この「勝ち負けをつけない」という考え方は、受験戦争の過熱と不登校を問題視した文部省(当時)が、臨時教育審議会の答申(一九八七年)の中で「個性重視」を謳うようになってから広まったものである。だが、勝ち負けをつけないのは学校教育のあり方として正しいのであろうか。問題は徒競走に順位をつけることではなく、徒競走で活躍できなかった子供が他の領域で活躍できるような環境を整えられているかどうかではないのか。
徒競走での上位入賞という稀少な地位は、その稀少性ゆえに価値がある。そうだとすれば、他の領域に別の稀少性をつくりだしていくのが競争と無競争の間を探る方法である。ある領域で画一的に競争をなくしてしまっても、それは徒競走という限られた領域における競争が見えなくなるというだけのことであり、子供たちの競争がなくなるわけではない。ならば、いろいろな競争の領域をつくり、一つの競争に負けることが決定的にその人を打ちのめさないようにするための工夫が求められるのではないだろうか。
その意味で、「個性重視」を謳って競争からこぼれ落ちた生徒の尊厳を守ろうとする措置は皮肉にも見える。というのも、そもそも競争とは個の重視と表裏一体だったはずだからである。歴史的に見れば日本では、個の能力の違いを認めない集団主義へのアンチテーゼとして、競争原理がとらえられてきた面がある。問題にすべきは、競争か無競争かの二者択一ではなく、競争の領域と、個々の結果が生み出す影響の範囲をどのように限定するか、という点であろう。
競争の領域を広げるという話題をもう少し掘り下げてみよう。徒競走でいつも負ける子供が、いじめられて不登校になったという一つの極端な(しかし、十分ありうる)例を考えてみる。その子供の身になってみれば、これは自分の存在をかけた友達との間の争いである。ではこの場合に、争いを避けて競うことはできるだろうか。
一つ目の観点は、勝敗の判定基準の多元化によって、勝敗を一つの基準で決めない方向性がある。たとえばスキーのジャンプ競技では飛距離だけでなく着地のフォームも評価の対象となる。競争の効果が及ぶ範囲の限定は、逆説的に聞こえるかもしれないが、競争の領域と内容を増やすことで可能になる。
二つ目の観点は、競争に負けた人の処遇である。そこには何らかの競争に敗れたメンバーを学校や会社といった集団としてどのように遇するか、そして敗者本人がそれをどう受け止めるか、という二つの課題がある。いていの競争では勝者になる人より敗者になる人が多いことを考えれば、これらの問題に上手く対処できるかどうかは、個々の集団の持続可能性に決定的な影響を与えるはずである。
住民同士の依存関係が深い伝統社会では、「負けの処理」に関する工夫が多く見られる。上手く処理できなければ共同体が壊れてしまうからである。一九六〇年代にメキシコの農村を研究した人類学者のジョージ・フォスターは、共同体の中で生じがちな羨望や嫉妬の気持ちを和らげることで「不幸の処理」の機能を果たしている文化的装置を発見した。それは、「善いものは数が限られているという世界観(Image of Limited Good)」である。フォスターの調査した集落では「望ましい物事―土地、富、健康、友情、愛、名誉などは限られた存在量しかなく、その供給は常に不足している」という世界観が共有されていたという。
この世界観は、他者の成功を偶然や幸運、運命など、人知の及ばない力に帰するときの助けになる。自分の能力が劣っている可能性をまともに認めなくて済むからである。失敗や不運は個人の能力不足によるものではないと納得することで、人々は精神的に打ちのめされることなく、最低限の自尊心を維持できる。
また、望ましいものが限られているとすれば、自分の利得向上は誰かの利得を減じることでしか達成できない。だからこそ集団の構成員は「善いもの」の獲得を自慢するようなことはせず無用な嫉妬をあおることを避けようとする。他より多くを所有する人々は、宝くじのような偶然のメカニズムで思いがけず恩恵をこうむることができたのだと他人に説明することで、無用な羨望を抑え込むのである。この世界観によって争いに発展しうる嫉妬や羨望を抑止できているとすれば、それは伝統的な共同体に特有の閉じた依存関係でこそ機能する工夫であると考えてよい。
「負けの解釈」を工夫する伝統は日本にもあった。第二次世界大戦の直後に出版された日本文化論の名著であるルース・ベネディクトの『菊と刀』は、当時、「異常なほどに好戦的」と思われていた日本人が、同時に風流なものを好むといった性格を合わせもつ点に着目し、その「矛盾」の深層にある行動原理に迫ろうとした。彼女の分析の中で特に興味深いのが、日本人の「負けるが勝ち」という価値観を論じている箇所である。
ベネディクトは、日本の子供がおもちゃをめぐってきょうだい喧嘩をしたときの母親の仲裁方法に注目する。母親は年長者である兄の方をこう諭す。「負けるが勝ちと言うでしょう。だから小さい子に負けてやりなさいな」。この場面に描かれているのは、目の前の負けた子供をその場しのぎで納得させ、「負けを受け入れる練習」をさせる様子だけではない。母親は「大きい子」の自尊心をくすぐりつつ、「遊び」を楽しくするには小さい子も大きい子も、それぞれ役割があるという、一段高いところに視点を誘導しているのである。負けの受け入れ方を工夫するのは、それが単に敗者の精神的な安定に役立つからではない。敗者が勝者にむやみに嫉妬することなく自分なりの道を歩めるよう励ますことになるからなのである。日本社会は、あからさまな負け組をなるべく生まないような工夫を様々な集団の中で重ねてきた。たとえば中央省庁の最高ポストである「(事務)次官レース」に敗れた官僚たちを外郭団体などで遇する「天下り」は、外部からみると官民の癒着の象徴である。しかし官の視点から見れば、入年次が上がるにつれて激化する出世競争に敗れた者たちを少しずつ納得させながら、組織のピラミッドを維持していくために有効な制度であった。格差に由来する対立を未然に抑え込む工夫も、私たちの生活世界には散りばめられている。たとえば「気前の良さ」をカッコいいと見なす風潮である。富を手にした者には気前よく振る舞う責務が生じるという社会的圧力は多くの地域で見られる。身近な例で言えば、会社の飲み会で上司が多く支払うような会計の慣習である。お寺の寄進にも似たような機能がある。お寺の本堂には、それぞれの檀家が寄進した金額が貼り出されていることが多い。この慣習には、顔を知った者同士の「気前の良さ」を競争させることで再分配の仕組みをつくり、共同体を持続させる役割がある。
争うことなく競うために「負けの処理」が重要になることは各地の事例の示すところである。本章では、メキシコの農村のように負けの解釈自体を変える方法や、勝者から敗者への部分的な再分配を行ったり、競争の負け組をしかるべく処遇したりする方法を紹介した。勝敗を個人の能力だけによるものと見ず、天の采配と解釈することで争いを目立たなくするのが、集団内での争いをエスカレートさせない一つの工夫なのであった。
競争は人間社会に多くの恩恵をもたらした。しかし、競争が「向き」を変えて争いに転化すると、競争の果実は台無しになる。大規模な争いともなれば、社会は疲弊して、地球環境は傷つく。今ほどの経済規模でなかった時代から、人類はこの危険性に気づき、様々な工夫を社会に内部化することで争いがエスカレートしないよう試みてきた。だが、依存関係が特定の集団内部に閉じていた時代の社会で見られた仕掛けは、その集団内部での心の均衡を保つのには役立つが、個人単位の競争心に立脚した近代資本主義の世界でも有効だろうか。グローバル化が進行した現在、競争の利点を受け入れつつも、その影響を節度ある範囲に収め、戦争に転化してしまうなど、競争の副作用が重症化することを未然に防ぐような工夫とはどのようなものであろうか。
一つのポイントは、競争の基準や対象をいかに顕在化させるか、もしくは顕在化させずにおくのか、という情報の操作である。伝統社会の方法に学んで、競争をあおるような序列を見えにくくし、争いを激化させる嫉妬や猜疑心を刺激しないよう意図的に曖昧さを残す工夫である。
あらゆる分野において、外から見たときの「分かりやすさ」を求めるのが現在の風潮である。だが棚上げされていた尖閣諸島領有問題が日本側の国有化宣言を発端に日中の対立を顕在化させたように、分かりやすさは争いを呼びこむことがある。明確な基準を頼りに分かった気になって忘れてしまうのではなく、まだよく分からないことを考え続けることこそ、争いの当事者らをつなぎとめる力になる。
なるほど、曖昧さは時に優柔不断や判断を遅らせるというコストを伴う。問題は、分かりやすさの中で置き去りにされるものをどのくらい重視するかであろう。たとえば、収益をめぐる競争環境の中で、どうにかして費用を節約したい企業が、悪いと知りながら廃棄物を不法投棄することがある。
その結果、気づかれないまま環境が劣化し、災害リスクが高まることもあるだろう。この種の問題の場合は、むしろ競争の基準を分かりやすく表に出すことで、利益勘定に反映できる範囲で争いへの歯止めをかけるべきであろう。他方で、領土問題など既に緊張の焦点が明らかなものについては、それ以上、事を大きくせずに曖昧に処理することの利点がある。そう考えると、曖昧さは、競争をそれぞれの領域に収めて、争いへの転化を防ぐための工夫であったとみることができる。
ただし、こうした工夫は国や地域という「外壁」に囲まれて、依存関係が閉じているときに機能するものである。国境や競技のルールなどの明確な枠組みがなければ、勝ち負けの問題ではなくなってしまうからである。勝ち負けの判定が避けられない場合はある。しかし、そうした場面を上手限定するところに、争わない社会への工夫の急所がある。
競争環境にさらされている諸個人は、どのような回路で社会に争いを展開していくのか。身の回りの集団のレベルで争いを収めることができなくなるのは単に個々人の意図や思惑の結果ではない。個と集団を健全な形で再び結び直し、競争が争いへと転化しないようにするには、競争によって可能になると考えられてきた自立や効率といった価値観そのものを見直さなくてはならない。
(佐藤仁『争わない社会「開かれた依存関係」をつくる』より)
設問
設問I
この文章を三〇〇字以上三六〇字以内で要約しなさい。
設問II
競争について、この文章をふまえて、あなたの考えを三二〇字以上四〇〇字以内で述べなさい。
文学部問題の考え方

要約に関して
第一問の「要約」に関して誤った考え方が横行しています。
「ともかく本文から該当箇所を引っ張って書く」という発想を捨てましょう。
大切なことは「理解している内容を自分の言葉で書く」ということです。
「自分の意見」に関して
第二問の「自分の意見」に関しては、以下の2つの点が重要です。
- 具体的事例を書くこと
- ともかく「未来志向」で考えること
解答例

それでは解答例です。
第一問
市場経済後、成長と結びついた競争は稀少性を対象とした。その判定基準が統一されて序列が明確化されると競争は激化し、争いに変わった。実際、競争原理には無形の価値や人間の依存関係および自然環境の損失などの限界が存在する。しかし無競争の状態も競争の歪みを解消する方法ではない。重要なのは、範囲と影響をどのように限定するかである。伝統社会では競争の判定基準の多様化と共に、敗者に適切な処遇を施して再分配のメカニズムを構築した。このような取り組みは、競争の基準や対象をあいまいにするか、あるいは明確にするかの操作に関わるものである。しかし、現代において個人レベルでの競争に晒されている状況で争いを減少させるためには、競争がもたらすとされる自立や効率といった価値観を見直し、個人と集団を健全な形で再結合させなければならない。(355字)
第二問
持続可能な競争機会を保持するためには競争の敗者への適切な対応が重要である。なぜなら競争とは、単に運や能力のみに基づくものではないからだ。つまり実際の競争は、すべての参加者が等しい条件下で競争に臨めるわけではなく、特定の個人に勝敗が偏る不公平な状況が生じているのだ。配慮が行われていたとしても、実際には勝つことが不可能な競争に参加しなければならない状況であれば、多くの人々にとって、競争は失敗の原因となる。
よって競争をより公平にすることが必要である。その実現のためには、すべての人が個人として競争できる状況を作ることが望ましい。例えば、2022年にリリースされたChatGPTにより、技術的障壁は低減された。そのことで多様な背景を持つ人々が個人として参加できる新たな競争の場を提供している。しかし、この新しい環境においても、時間が経つにつれて、環境に適応できる人々とそうでない人々に分かれていくことになる。公平な競争を維持するためには、個人が持つ背景や条件に関わらず、運と実力のみで争う競争の場を創出し続けることが求められる。
鍛錬場で頑張ろう!
鍛錬場では、このような幅広いコーチングサービスを提供しています。
ぜひ以下にアクセスして下さい。
鍛錬場の紹介ページはこちらから